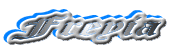 (4)
(4)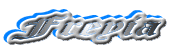 (4)
(4)
子どもが生まれた喜びも、父親としての感慨も、仕事は待っていてくれない。
子育てに奔走するエヴァと、
特例で自宅から士官学校に通うことを許されたハインリッヒ・ランベルツのふたりに家庭のことを任せて、
ミッターマイヤーは「帝国のため」超多忙な日々を送ることになった。
皇帝アレク陛下には摂政として皇太后ヒルダがついているが、
実質的な国政は自分が担わなければならない。
こんなはずじゃなかった、と、愚痴も出ようというものだ。
「さっさと死んだおまえが悪いのだぞ、ロイエンタール。
おまえがいればこんなことは全部おまえに押しつけて、おれは宇宙を駆け回るのにな」
おまえこそ虫がよすぎるぞ、とロイエンタールの声がしたような気がした。
なれない文官の仕事はなかなかに大変だ。
しかしマリーンドルフ伯はミッターマイヤーのためにこれ以上ないほどに環境を整えていた。
日を追うごとに仕事が能率的になっていき、そしてミッターマイヤーはいくつかのことを学んだ。
すべてを自分で背負うのではなく、適所に分散させるのも仕事のうちだということ。
自分は部下を使う立場にある。
自分が出しゃばっていては、そのうち自分の首を絞めることになる。
自分が向いていないことがあるのであれば、そこには向いている人材を登用すればいい。
これは軍も同じだ。
幸い文官として有能な二人ーカール・ブラッケとオイゲン・リヒターをラインハルト陛下が残してくださっている。
彼らは自分の理想とする社会の実現のため、ミッターマイヤーを祭り上げておこうと思っているようだ。
なら自分もそれに乗ろうではないか。
こちらも二人を利用する。
お互い持ちつ持たれつ、というやつだ。
元来彼はこういう駆け引きは苦手だったがそうも言っていられない。
バーラト星域の共和主義者のことも気になるが、まずは自治権で満足していただこう。
そのあとのことは・・・
国を治めていくときに、敵がいないと言うことは実は一番危険だ、ということも学んだ。
外に敵がいなくなれば、市民の関心は内と向かう。
そして(特にマスコミというものは)批判することが自分たちの使命と思っているふしがある。
彼らの関心と批判の矛先は、ぜひ共和主義者たちの方にむいてほしい。
では、生かさず、殺さず。
適度に友好関係を維持しつつ、距離を置いて。
近づきすぎると危険だ。
この国はまだ生まれたばかり。
共和主義は、まだこの国には毒となる。
しかし、少しずつ毒を飲み込み、耐性を作る必要はある。
共和主義者の連中は、議会がどうのこうの、と言っていたな。
議会か、それもよし。
では自分もその議会とやらを利用すればいい。
難しいことをしているなと、自分で自分がおかしくなることもある。
しかし、自分以外のだれがそれをするのだろうか?
政治は自分の手をきれいにしたままではできない、ということも学んだ。
あれほど嫌っていたオーベルシュタインが今ここにいたなら・・・と思うこともある。
今なら、もう少し好意を持ってみることができたかもしれない。
政治のアンダーグラウンドな部分はオーベルシュタインの部下だったフェルナーが助言してくれる。
ヒルダやアレク陛下の手を汚すわけにはいかないのだ。
そのかわり自分の手はもう血まみれになっている。
新しい国には新しい象徴も必要だ。
それはアレク陛下とヒルダ皇太后、そして大公妃アンネローゼにお願いしよう。
しかしここまで変わっている自分を、まわりはまだ「公明正大な疾風ウォルフ」として見ている・・・なら、それも演じねばならない。
理想の夫、理想の家族というものを、だ。
自分には似合わないことをやっていることをミッターマイヤーは自覚している。
しかし、自分は生き残った、いや、生き残ってしまった。
これは生き残ったものの責務なのだ。
意外なことを発見した。
自分の副官たち−バイエルライン、ビューロー、ドロイゼン、ジンツァーは意外と適応能力がある、ということだ。
ビューローは執政官としても有能な面を発揮している。
ドロイゼンは、これも意外なことに、スポークスマンとしての才を発揮している。
今や国務省の顔となりつつあるのだ。
ジンツァーは統帥本部次長として、総帥本部長メックリンガーをしっかり補佐し、日々職務に励んでいる。
バイエルラインは・・・「次期宇宙艦隊司令長官」などと軽口をほざいていたが、今や国務尚書の右腕として常にそばにいてくれる。
宇宙を駆けるよりも、敬愛する上官と共にあることを望んだのだ。
ミッターマイヤーの護衛であり、参謀であり、有能な秘書の一人である。
その青二才ぶりもこうなると国民にとっては「愛すべきキャラクター」となっているようで、テレビでの露出度も高い。
ミッターマイヤーが細心の注意を払ってアレクの私生活をさらさないようにしていることもあって、
ミッターマイヤー家とバイエルライン家はある意味国民の注視の的であった。
そして、その面ではバイエルラインは合格だった。
彼は愛妻家ぶりまで敬愛する上司に負けず劣らずだったのだ。
蜂蜜色の髪の奥方も穏やかな人柄で、周囲に愛されている。
上司と違い早々と子どもにも恵まれ、なかなかに幸せな家庭を築いているようだ。
執務中に、バイエルラインがミッターマイヤーをじっと見つめていることがある。
ミッターマイヤーは気がついているが、あえて気がつかないふりをする。
あの表情は何なのだろう?
同情?違う、と思いたい。
哀れみ?そこまで自分は落ちぶれていない。
答えはわかっていると思うのだが、あえて考えないミッターマイヤーである。
(5)へ
今回は少々暗い・・・わたしの偏った国家感がにじみ出てきているような気がする。